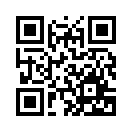2015年10月11日
学級作りの基礎は、レクで
ルールとリレーション
が、あってこそのアクティブラーニング
そのルールと、リレーションの支点で、レクが役立つのではないかと考える。
以下、私も直接お話を伺う機会があった先生の学級作りの講義があったので。。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ 学級集団づくりと学級リーダーの育成
早稲田大学大学院・総合科学学術院教授 河村茂雄
○学級集団づくりを基にした学級経営は,
・自己管理力を自己教育力のある集団の形成に関与することを通して,すべての児童
生徒に自己管理力と 自己教育力を育てることが究極の目標
↓
・学級集団での活動や生活を通して,すべての児童生徒のリーダー性,フォロアー性
を育てる。
1)すべての児童生徒にリーダー性,フォロアー性を学習させる。
2)支え合い,学び合い,そして高め合う学級集団の状態をつくる。
・・・
○学級経営が混沌とした中で,教師たちは自信をなくしている。
・できない→意識から薄れている→重要視しない
・できている→個人的自信,名人芸→教員間で共有されない
○うまくいっている学級集団にはどのような相互作用が働いているのか
○良好な学級集団はどのように形成されるているのか
○教師はどのような対応をしているのか
○活用することが前提
1)居心地のよいクラスにするために
2)やる気のあるクラスにするために
3)日常の行動をふり返るアンケート,ソーシャルスキル
学級集団の状態のAssessment‥‥理想の学級集団の構造
○学習指導要領,学級経営に関する先行研究の整理から教師が望ましいと考える学級集
団の最大公約数
・必要条件
1)集団内の規律,共有された行動様式(ルールの確立)
2)集団内の子ども同士の良好な人間関係,役割交流だけではなく,感情交流の含ま
れた内面的なかかわりを含む親和的な人間関係(リレーションの確立)
↓
・十分条件
3)一人ひとりの子どもが学習や学級生活に積極的に取り組もうとする意欲と行動す
る習慣
同時に子ども同士で学び合う姿勢と行動する習慣
4)集団内に,子どもたちの中から自主的に活動しようとする意欲,行動するシステ
ム
12 学級集団を見る視点‥‥ルールとリレーション
○ルール → 集団で安心して生活するための基本的なルール
⇔ ‥‥このバランスがとれていると集団は安定する。
○リレーション → 安心して本音を言い合えるような人間関係
16 満足型の学級集団の教育的作用
・意欲の喚起 ・意欲の維持 ・モデル学習 ・活動する習慣
↓
アクティブラーニングが成立する学習集団の環境
→自ら考え,判断し,表現する力の育成や学習に取り組む意欲を養うことが教育
理念
小・中・高等学校でも学習者主体の授業の展開が求められる。
17 アクティブラーニングの実質化
○学習者の主体的な学習参加があること
○学習者同士の能動的な相互作用による学習が生起されること
○学習者が安心して自分の考えや意見を発現できること
○学習者同士が率直に交流できる一定のルールの共有と人間関係がある環境が不可決
18 学習集団づくりとともに展開する学級リーダーの育成 その1
1)混沌・緊張期‥‥児童生徒たちの意識性を高め,方法を共有させる段階
教師がモデルとなる行動をとりながら児童生徒たちにそのような行動の意義を説明
し,その方法を教えていく段階
2)混沌・緊張期~小集団成立期‥‥コアメンバーを形成する段階
学級内の相対的に意識性の高い児童生徒たちが,教師の説明と行動をモデルにして
行動し,リーダーシップをとるようになる段階
3)小集団成立期~中集団成立期‥‥リーダーシップをとる児童生徒がローテーションし
ていく段階
教師や意識性の高い児童生徒たちの行動が他の児童生徒たちに広がり,新たに意識
性が高まった児童生徒がリーダーシップをとれるようになる段階
4)中集団成立期~全体集団成立期‥‥おとなしい児童生徒もリーダーシップをとれるよ
うになる段階
まわりの児童生徒たちが能動的にフォロアーシップを発揮することができ,その中
でおとなしい児童生徒もリーダーシップをとれるようになる段階
5)全体集団成立期~自治的集団成立期‥‥すべての児童生徒がリーダーシップをとれる
ようになる段階
活動の内容に応じていろいろな児童生徒たちがリーダーシップやフォロアーシップ
を柔軟にとれるようになる段階
が、あってこそのアクティブラーニング
そのルールと、リレーションの支点で、レクが役立つのではないかと考える。
以下、私も直接お話を伺う機会があった先生の学級作りの講義があったので。。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ 学級集団づくりと学級リーダーの育成
早稲田大学大学院・総合科学学術院教授 河村茂雄
○学級集団づくりを基にした学級経営は,
・自己管理力を自己教育力のある集団の形成に関与することを通して,すべての児童
生徒に自己管理力と 自己教育力を育てることが究極の目標
↓
・学級集団での活動や生活を通して,すべての児童生徒のリーダー性,フォロアー性
を育てる。
1)すべての児童生徒にリーダー性,フォロアー性を学習させる。
2)支え合い,学び合い,そして高め合う学級集団の状態をつくる。
・・・
○学級経営が混沌とした中で,教師たちは自信をなくしている。
・できない→意識から薄れている→重要視しない
・できている→個人的自信,名人芸→教員間で共有されない
○うまくいっている学級集団にはどのような相互作用が働いているのか
○良好な学級集団はどのように形成されるているのか
○教師はどのような対応をしているのか
○活用することが前提
1)居心地のよいクラスにするために
2)やる気のあるクラスにするために
3)日常の行動をふり返るアンケート,ソーシャルスキル
学級集団の状態のAssessment‥‥理想の学級集団の構造
○学習指導要領,学級経営に関する先行研究の整理から教師が望ましいと考える学級集
団の最大公約数
・必要条件
1)集団内の規律,共有された行動様式(ルールの確立)
2)集団内の子ども同士の良好な人間関係,役割交流だけではなく,感情交流の含ま
れた内面的なかかわりを含む親和的な人間関係(リレーションの確立)
↓
・十分条件
3)一人ひとりの子どもが学習や学級生活に積極的に取り組もうとする意欲と行動す
る習慣
同時に子ども同士で学び合う姿勢と行動する習慣
4)集団内に,子どもたちの中から自主的に活動しようとする意欲,行動するシステ
ム
12 学級集団を見る視点‥‥ルールとリレーション
○ルール → 集団で安心して生活するための基本的なルール
⇔ ‥‥このバランスがとれていると集団は安定する。
○リレーション → 安心して本音を言い合えるような人間関係
16 満足型の学級集団の教育的作用
・意欲の喚起 ・意欲の維持 ・モデル学習 ・活動する習慣
↓
アクティブラーニングが成立する学習集団の環境
→自ら考え,判断し,表現する力の育成や学習に取り組む意欲を養うことが教育
理念
小・中・高等学校でも学習者主体の授業の展開が求められる。
17 アクティブラーニングの実質化
○学習者の主体的な学習参加があること
○学習者同士の能動的な相互作用による学習が生起されること
○学習者が安心して自分の考えや意見を発現できること
○学習者同士が率直に交流できる一定のルールの共有と人間関係がある環境が不可決
18 学習集団づくりとともに展開する学級リーダーの育成 その1
1)混沌・緊張期‥‥児童生徒たちの意識性を高め,方法を共有させる段階
教師がモデルとなる行動をとりながら児童生徒たちにそのような行動の意義を説明
し,その方法を教えていく段階
2)混沌・緊張期~小集団成立期‥‥コアメンバーを形成する段階
学級内の相対的に意識性の高い児童生徒たちが,教師の説明と行動をモデルにして
行動し,リーダーシップをとるようになる段階
3)小集団成立期~中集団成立期‥‥リーダーシップをとる児童生徒がローテーションし
ていく段階
教師や意識性の高い児童生徒たちの行動が他の児童生徒たちに広がり,新たに意識
性が高まった児童生徒がリーダーシップをとれるようになる段階
4)中集団成立期~全体集団成立期‥‥おとなしい児童生徒もリーダーシップをとれるよ
うになる段階
まわりの児童生徒たちが能動的にフォロアーシップを発揮することができ,その中
でおとなしい児童生徒もリーダーシップをとれるようになる段階
5)全体集団成立期~自治的集団成立期‥‥すべての児童生徒がリーダーシップをとれる
ようになる段階
活動の内容に応じていろいろな児童生徒たちがリーダーシップやフォロアーシップ
を柔軟にとれるようになる段階
Posted by 未来 at 12:19│Comments(0)